|
1.魚類の病原細菌
魚病細菌ともよばれ、現在では魚介類の病原細菌は40種以上知られていますが、そのほとんどが魚類の病原細菌です。ここでは筆者らが研究した魚類病原菌を含めて、主な細菌病とその原因菌について述べます。
1)せっそう病とその原因菌
せっそう病は、19世紀末にドイツで最初に報告され、最も古くから知られた代表的なサケ科魚類の細菌病の一つです。この魚病の典型的な症状は、病魚の体側部に膨隆した患部ができることで、それはかつて“せっそう”とよばれていました。後になって、その医学用語が誤認であったことが判りましたが、長年の慣用でこの病名になっています。
この魚病は現在オーストラリアとニュージーランド以外の全世界に広がっています。日本では1929(昭和4)年頃から長野県でニジマスに発生して以来、主に淡水性のアマゴ、ヤマメ、ヒメマス、イワナなどに被害が及び、現在はサケ科魚類のほとんどと他の魚類にも感染することが知られています。
症状は進行すると体表に膨隆部が生じ、筋肉、内臓(腸管、肝臓、腎臓)などに出血や潰瘍化がおこり遂には死亡します。
せっそう病菌は、エロモナス・サルモニシダです。サルモニシダはサケを殺すという意味です。形は短い桿(棒)状(長さ:1〜2マイクロメートル)で、菌体の外へ褐色色素(メラニン様)を出すことが特徴です。後述しますが、同種で褐色色素を出さない亜種もあります。
一般に病原菌がもっていてその症状をおこす原因物質を病原因子または毒力(性)因子といいます。せっそう病菌の病原因子として、この細菌の細胞構成体、菌体の外へ出す毒素(白血球溶解因子、溶血毒素)や酵素(タンパク質分解酵素)が知られています。
筆者らはその一つである溶血毒素(魚の赤血球を溶かす物質)を初めて単離(純粋な物質として分離・精製すること)して、その詳しい性状を明かにしました。その結果、高分子(大きな分子)の糖タンパク質であることが判り、せっそう病菌の学名からその溶血毒素をサルモリジンと命名(サルモはサケの意、 リジンは溶かす毒素の語尾)しました。また、この毒素を無毒化したトキソイド(抗原)を魚へ接種すると、魚体内でその抗体ができてせっそう病の感染・発病を抑えることが確認されました。
せっそう病の治療には、サルファ剤や抗生物質が有効ですが、耐性菌が問題になっています。そこで、予防としてノルウエーでは注射ワクチン(抗原として体内へ接種するとその抗体ができ、発病を防ぐ物質)が用いられていますが、日本ではまだ実用化されていません。
なお、淡水魚の穴あき病とウナギの頭部潰瘍病などの原因菌もせっそう病菌と同属、同種ですが、褐色色素を出さず、その他の性質も違っていますので、せっそう病菌の亜種(非定型)とされています。
2)ビブリオ病とその原因菌
ビブリオ病は、広く淡水・汽水・海水性魚類の病気で、せっそう病と並んでヨーロッパで最も古くから知られていた細菌病の一つです。すでに18世紀からヨーロッパではウナギのレッド・ペストとよばれていた魚病ですが、その後、北アメリカ、オーストラリア、日本にも広がり、最近は世界的にサケ科魚類にも多発して問題となっています。日本ではニジマスなどのサケ科魚類のほかアユ、ブリ、マダイなどの養殖海産魚にも発生しています。
症状は外見的な病変はあまりなく死亡する場合もありますが、多くは体表、ひれ、えら、肛門の周り、内臓などに強い出血がみられ、慢性では体表に潰瘍ができます。
ビブリオ病菌は、ウナギの学名からビブリオ・アンギュイラルムと命名されました。細菌の形は、鞭毛で運動するコンマ状(長さ:1〜2マイクロメートル)で、人の病原菌であるコレラ菌や腸炎ビブリオも同属です。
ビブリオ病菌の病原因子として、その細胞の構成体や菌体の外へ出す毒素などが研究されました。筆者らもこの病原菌の溶血毒素を研究して、それが100℃でも安定で、しかもその活性が増加する耐熱性の酸性多糖(グルコースのような単純な糖類が多数結合した物質)であることが判りました。人の腸炎ビブリオもこれに似た耐熱性の溶血毒素を出します。
ビブリオ病の治療としてはフラン剤、サルファ剤、抗生物質が有効ですが、耐性菌が問題化しています。予防には1990(平成2)年頃から魚病ワクチンとしては唯一の浸漬ワクチンが開発・市販されています。
3)カラムナリス病とその原因菌
カラムナリス病は、1922(大正11)年にアメリカで温水魚に発生し、その後、川へ遡るサケ科魚類、ウナギ、コイなどの淡水・汽水魚に感染して広く世界に分布しています。
病名は患部にできる特徴的な黄色い柱状(カラム)の細菌塊に由来しています。日本では1965(昭和40)年頃からウナギの養殖が盛んになり、その配合飼料が使われるようになってからこの魚病が広がったといわれています。
ウナギでの症状は、主にえらやひれが冒され、うっ血や出血がおきさらに組織が崩壊して死亡します。ほかの淡水魚では口や皮膚が冒されますが、どの場合でも患部は直接水に接する部位に限られ、普通は内臓に異常はみられません。
カラムナリス病菌は、従来は滑走細菌のフレキシバクター属、その後はシトファーガ属の1種とされていましたが、1996(平成8)年にフラボバクテリウム・カラムナーレとされています。
この細菌は細長い桿状(長さ:3〜8マイクロメートル)で黄色色素をもっています。その特徴は菌体を揺れ動かす屈曲運動や固体の表面(スライド・ガラスや寒天培地)をゆっくり滑る滑走運動をすることです。
この細菌の病原因子についてはまだ確定されていないのですが、筆者らはこの魚病の特徴から毒素性ではないと考え、この細菌が出すタンパク質分解酵素に着目して、その酵素を分離して性状を調べたところ、マンガンと結合した比較的まれな酵素(マンガン酵素)であることが判りました。
ところで、前述したように養殖ウナギの配合飼料が多用されて以来この魚病が広がったといわれていますが、その配合飼料にはミネラル分としてマンガンが含まれています。
つまり、養殖魚の栄養分が魚病細菌の栄養分でもあるという皮肉な現状があるのです。したがって、養殖魚の病気対策の一つとして、配合飼料のことも考慮する必要があります。なお、治療には初期にサルファ剤や抗生物質が有効です。
4)連鎖球菌症とその原因菌
連鎖球菌症は、1974(昭和49)年に高知県のブリ養殖場で発生して以来、全国に広がって養殖ブリに大きな被害をもたらしています。ブリのほかマアジ、イシダイ、ヒラメなどの海水魚やアユなどの淡水魚にも発生しましたが、現在は海産魚の代表的な細菌病の一つです。
症状は一般的には眼球の白濁や突出、えら蓋の発赤や膿瘍、心臓内膜炎などが特徴ですが、ときに外観的には異常がみられなくても、脳障害で狂ったように泳ぐ場合があります。
ブリやマアジの連鎖球菌症の原因菌は、最初ストレプトコックス属の1種、のちエンテロコックス・セリオリシダとされましたが、1996(平成8)年にラクトコックス・ガルビアエとされています。また、イシダイ、ヒラメ、アユの連鎖球菌症の原因菌は、ストレプトコックス・イニアエです。これは淡水イルカの連鎖球菌症の原因菌でもあります。
その形は運動しない球状(0.7×1.4マイクロメートル)の細胞が多数連鎖しています。両菌ともに病原因子として、赤血球を溶かす毒素(溶血毒素)をもっていることが特徴です。治療には抗生物質が有効です。変わった方法として、この細菌のウイルス(ファージ)による治療法が研究されています。
5)その他の魚病細菌
魚病細菌は上記のほかに多種類が知られています。その主な魚病と原因菌を挙げます。
(1) 淡水魚の運動性エロモナス症(ひれ赤病など): エロモナス・ヒドロフラ
(2) ウナギ、アユの赤点病: シュードモナス・アンギュイセプチカ
(3) サケ科魚類、アユの冷水病: フラボバクテリウム・プシクロフィルム
(4) サケ科魚類の細菌性腎臓病: レニバクテリウム・サルモニナルム
(5) 淡水・海水魚のエドワジエラ症: 主にエドワルドジエラ・タルダ
(6) ブリの類結節症: フォトバクテリウム・ダムセラエの亜種ピスシシダ
(7) ブリのノカルジア症: ノカルジア・セリオラエ
なお、ウイルスと同様に細胞内だけで増殖する最小細菌のリケッチアとクラミジアも魚病細菌として知られています。外国で淡水フグ(ナイル川)のほか、テラピア、ハタ、スズキ、熱帯魚、ギンザケのピシリケッチア症が報告され、ギンザケではリケッチア・サルモニスが原因です。また、淡水・海水魚のエピテリオシスチス病の原因はクラミジアです。
2.甲殻類、貝類などの病原細菌
細菌病が報告された魚類以外の水産動物(魚介類)には、現在、増・養殖されているエビ、カニとカキ、アワビやウニがあります。そのほかにクジラ、イルカ、オットセイなど(哺乳類)、ウミガメやスッポン(爬虫類)、カエル(両生類)など水生動物の細菌病もあります。
1)甲殻類の病原細菌
甲殻類の中でもとくに養殖クルマエビのビブリオ病は、日本では1980(昭和55)年頃から広がり、日本や東南アジアでエビの幼生や成エビに大きな被害をもたらしました。
その主な原因菌は、エビの学名に由来するビブリオ・ペナエイシダで、南西太平洋のニューカレドニアでもブルーシュリンプのビブリオ病がこの細菌によると考えられています。また、日本ではガザミの幼生もある種のビブリオに感染したと報告されています。
これらは飼育水や一見健康にみえるエビにも常在して、その水質悪化やストレスによって発病すると考えられています。主な症状は、リンパ様器官や中腸腺が冒されることで、進行すると死亡します。治療には抗生物質のオキシテトラサイクリンが有効で、予防には死菌ワクチンや免疫性を高める薬剤(免疫賦活剤)の投与が有効であると報告されています。
また、北アメリカやヨーロッパの大西洋沿岸に生息するアメリカン・ロブスターやヨーロピアン・ロブスターにはガフケミアという古くから知られた病気があり、その原因菌は四連球菌のエロコックス・ヴィリダンスで、血液寒天培地での集落の周りが緑色になることが特徴です。この細菌は、ロブスターの血リンパ液に侵入し、その液が凝固しなくなり、遂には敗血症で死亡させます。ヴィリダンスは緑色の意味です。
なお、筆者は以前にアメリカの東海岸にあるロブスター養殖場でこの細菌を顕微鏡で観察した経験があります。ただし、この細菌は日本には存在しません。
そのほかにエビやカニの甲羅が冒される甲殻病菌(バチルス属のキチン分解菌)や病原性はないエビのえら着生菌(滑走細菌:ロイコスリックス・ムコール)があり、淡水ザリガニにはリケッチア症菌(コキシエラ・ケラックス)が知られています。
2)貝類とウニの病原細菌
アメリカではアメリカガキの人工種苗の幼生にビブリオ病が発生して問題になりました。原因菌は、ビブリオ・ツビアシイほか数種のビブリオです。日本ではカキの細菌病はないのですが、トリガイの幼生にある種のビブリオが原因の病気が発生し、アワビにもビブリオ・アンギュイラルムが原因する細菌病が報告されています。この細菌は魚類のビブリオ病菌と同じです。そのほかアメリカではクロアワビのリケッチア症が知られています。
一方、北海道のエゾバフンウニに斑点症が発生し、その原因菌は滑走細菌のフレキシバターとされています。
3)水生哺乳類、爬虫類、両生類の病原細菌
水族館や動物園で飼育されている水生動物も細菌病に罹ります。その主な細菌病に、哺乳類ではクジラのサルモネラ症、クジラ、バンドウイルカ、サカマタ、アシカ、アザラシ、オットセイのクロストリジウム症があり、それぞれの原因菌の属から病名になっています。
また、前述しましたが、淡水イルカには連鎖球菌ストレプトコックス・イニアエによる感染症があります。
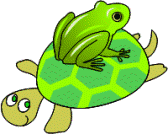 爬虫類ではウミガメやスッポンの 出血病、両生類ではカエルの 赤肢病があり、これらの病原菌は魚類の ひれ赤病菌と同じエロモナス・ヒドロフィラです。また、ウミガメにはほかに哺乳類と鳥類の結核菌や魚類の ミコバクテリウム症菌と同属の病原菌が知られています。なお、ペットとして飼育されるアオガメはときにサルモネラをもっています。サルモネラやクロストリジウムのある種は人の食中毒の原因菌でもありますので、これらの動物との接触には注意する必要があります。
第五章 水生動物の病原真菌
普段は水中に生息する真菌、とくにカビが水質変化や負傷などで不健康になった水生動物に真菌感染症(真菌病)をおこしますが、有効な治療法が少ない現状でその被害も無視できません。
1.魚類の病原真菌
現在、真菌は、動物界、植物界と並んで菌界とされ、接合菌類、担子菌類、ツボカビ類、子嚢菌類、不完全菌類に分けられています。以前はこのほかに鞭毛菌類としてミズカビ類(卵菌類)も真菌に含まれていたのですが、最近、ミズカビ類は菌界とは別の新しく提唱されたクロミスタ界の卵菌類に分類されています。
一方、これまでツボカビ類とされていたデルモシスチジウム・サルモニス(魚類の病原体)は、現在、菌界から原生生物界の原生動物(原虫)へ移されています。
また、同様にこれまで接合菌類のハエカビ類とされていたイクチオフォヌスも現在、原生生物界の原生動物に分類するという提案があります。
しかし、これらの病原体は以前から代表的な魚病真菌とされてきましたので、ここではこれらを含めて主な病原真菌について解説します。
表5.水生動物の病原真菌
|
 「主な対象読者」
「主な対象読者」
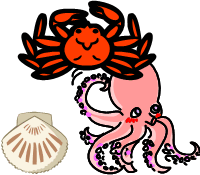
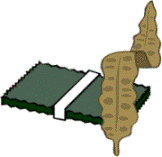
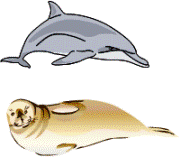 十数年前、シベリアの淡水湖であるバイカル湖に生息しているバイカル・アザラシの病気が問題になりました。その原因としてある種のウイルスが疑われていますが、詳しいことは明らかになっていません。
十数年前、シベリアの淡水湖であるバイカル湖に生息しているバイカル・アザラシの病気が問題になりました。その原因としてある種のウイルスが疑われていますが、詳しいことは明らかになっていません。
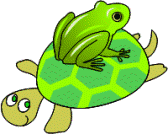 爬虫類ではウミガメやスッポンの出血病、両生類ではカエルの赤肢病があり、これらの病原菌は魚類のひれ赤病菌と同じエロモナス・ヒドロフィラです。また、ウミガメにはほかに哺乳類と鳥類の結核菌や魚類のミコバクテリウム症菌と同属の病原菌が知られています。なお、ペットとして飼育されるアオガメはときにサルモネラをもっています。サルモネラやクロストリジウムのある種は人の食中毒の原因菌でもありますので、これらの動物との接触には注意する必要があります。
爬虫類ではウミガメやスッポンの出血病、両生類ではカエルの赤肢病があり、これらの病原菌は魚類のひれ赤病菌と同じエロモナス・ヒドロフィラです。また、ウミガメにはほかに哺乳類と鳥類の結核菌や魚類のミコバクテリウム症菌と同属の病原菌が知られています。なお、ペットとして飼育されるアオガメはときにサルモネラをもっています。サルモネラやクロストリジウムのある種は人の食中毒の原因菌でもありますので、これらの動物との接触には注意する必要があります。