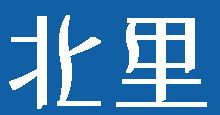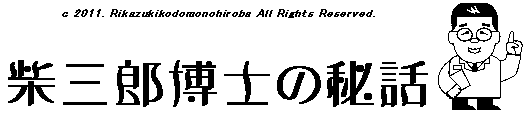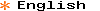第1章 北里闌(たけし)の誕生
第2章 大学時代からドイツ留学
第3章 日本語源の探索
第4章 後世への遺物
おわりに
|
21.北里蝋管に録音されていたもの
|
|||
|
土田 滋 順益台湾原住民博物前館長 北里闌(1870-1960)は明治3年、熊本県阿護郡北里村に生まれた。細菌学者の北里柴三郎は最長の従兄にあたる。同志社から國學院に転学し、国語国文学を学んだのちドイツに留学。ベルリン大学で5年学び「枕草紙」を独訳して、ドイツに紹介した功績がある。 博士号を取得して帰国したあとは、現在の大阪大学医学部の前身である大阪医科大学で、倫理学とドイツ語を教えたが、若いときから抱き続けた「日本語の起源」にたいする探求心止みがたく、ついに意を決して定年前に退職し、日本語起源の追求に一生を捧げることにした。一種の奇人と言ってよい。
詳細は略するが、彼は沖縄の言葉が一般に日本語の古い状態をよく保存している点と、日本語の五十音図の構成から、古代日本語にはア、イ、ウの3母音しかなく、一方、子音はk、g、c(シャ)、j(ジャ)、t、d、n、p、b、m、y、l、v、s、hの15子音だったと推定した。そしてそれを証明するために、当時のラッパ管付きの重い蓄音機と、何十本にもおよぶ蝋管をかついで、北は北海道から南はボルネオまで駆け歩いたのである。 幸いなことに北里闌は「日本語の根本的研究」(大阪:紫苑会、昭和5年)、「日本語源研究の道程」(同上、昭和5年、昭和7年増補)という大著を著わしており、録音内容を詳しく記録しておいてくれたので、その大要を知ることができる。それによれば、録音資料は大別して次の4つに分けられる: (1) 北里闌の自己紹介と、自分が何の目的でその地を訪れたかを、その地の言語あるいは方言に翻訳してもらった挨拶文、 (2) 日本語の母音「ア、イ、ウ、エ、オ」、 (3) その地の民謡とその簡単な説明、 (4) その他。 北里の挨拶文とは次のようなものである。少し長いが、彼の考えがよく解るから、ここに全文を引用しておこう: 「私は日本語原の研究に参った者であります。日本の古代語音と当地の語音とは元来同じ根底の上に立って居るものでありますから、出来得る限り、各地の方言を此の蓄音機に入れて頂きたいのです。その故は自分の多年の研究の結果、日本の古代語音は現代の五母音で無く、アイウの三音であったこと、子音が十五であったことなどが、その組織に於いて、全く此の地の方言と一致するからであります。それで成るべく他国語の影響を受けて居ない、純粋の語音を聞かせて頂き度いのです。 さて、此の蓄音機に入れて頂く理由は、私は永く当地に留まって研究することが出来ないので、今この器に入れて頂いた言葉を日本内地に持ち帰って、猶十分に研究したいからであります。何卒皆さん、ご迷惑でこざいませうが、私の此の学問的研究を助けると思って、御同情を願ひたいのです。 第一、入れて頂きたいのは、古来のアイウエオ(若しくはイロハ)の発音です。 第二、成るべく昔からある歌、民謡であります。古い歌などの声は比較的時代を超越して、 昔の音が其侭に聞かれるからであります。子守歌もあれば是非御願いしたいのです。 第三、この歌は何時頃からあったものとか、又どういふ時に唱ふもので、その意味は普通の言葉で言へばどんなものであるといふ説明です。 これで私としては三通り聞かれる訳です、どうぞ宜しく御願ひ致します。前以て 皆様の御好意に対して、厚く御礼を申上げます。」 つくづく惜しいなと思わざるを得ないのだが、北里闌氏はどうして言語学者に少しでもいいから相談しなかったのだろう? 比較言語学について、などという高尚なことではない。そうではなくて、はるばる台湾の山の中へまで蓄音機をかついで行くのならば、何を録音すればもっとも効率よくその言語の特徴をつかめるか、あるいはせめて、上の第一や第二を録音したらどういう結果が得られるか、についてである。 上述した通り、彼は古代日本語は3母音しか持っていなかったと信じており、だから台湾やフィリピンの言語こそが日本語の先祖だと至極単純に考えた。たしかにタガログ語やビサヤ語などは基本的に「ア・イ・ウ」の3母音しかない。だから、せっかく日本語の5母音を発音してもらっても、「ア・イ・ウ・イ・ウ」となるにきまっている。 もっともフィリピンや台湾の多くの言語は /a, i, u, @/(@ はシュワー、中舌母音、曖昧母音とも言われる)の4母音体系を持つのだが、日本人の耳には /u/ と /@/ の区別はつかないのが普通だから、北里氏が少しくらいその言語を調べてみても、やっぱり3母音しかないという結論しか出なかったろう。 第一の挨拶文の翻訳は、高砂族の言語のように文字を持たない言語の場合は大変だったろう。おそらくカナ書きしたものを頼りに読み上げたのだろうが、内容もさることながら、現在で言うリーディング・スタイルよりもっと悪い、棒読みスタイルとでも言おうか、言語資料としてほとんど価値がないのはまことに残念なことだった。 第二の民謡の類だが、言葉の聞き取りは無理でもメロディーはよく聞き取れるから、これがこの北里蝋管の中でももっとも価値が高いと言えそうである。 第三のその他には雑多なものが含まれる。たとえば蝋管番号239番の後半部は録音状態・保存状態ともによく、おそらくネイティブ・スピーカーならば聞き取り可能かと思われた。蝋管に付されたラベルと、「日本語の根本的研究」の記載とを照らし合わせると、この蝋管には台湾東海岸の台東のアミ族村落・馬蘭社で民謡などを録音した後、北里のお礼の言葉と、それに対するアミ族男子ウラオの答辞が録音されているらしい。 私はなにがしかの希望をもって、台東のアミ族出身の小学校の先生に、このテープを聞いてもらった。しかし蝋管に録音された声を聞き分けるのがいかに難しいかを、いやというほど思い知らされた。ああも聞こえるしこうも聞こえるというわけで、たった2分足らずの録音を、半日かかって聞き返し聞き直ししてもまだ終わらない。すったもんだの末、どうやら次のような内容らしいと言うのだ: ウラオ「私は使命を果たした。けれどもこの目で見るのではないから、この人が[=つまり北里が][日本に帰ってからあとでこの蝋管で]どういうことをやるのか判らない。フトル[=人名]が言うには……。私の考えでは誰が良いか[=合っているか]、誰が悪いか[=間違っているか][判らない]。この話が出てきて、合うようなことがなければ、恥ずかしい。」 つまりこのウラオは、北里がいったい何の目的で、大きなラッパの中に声を吸い取って行ったのか、わけが解らなかったのだろう。間違ったことを言わなかったか、あとで恥をさらすことになりはしないか、そればかりが心配だったに違いない。通訳は馬蘭公学校校長・アミ族のラワイが行なったとある。ラワイ校長も、おそらくは適当に立派な日本語で、しかるべき答辞風に通訳をしたのだろうが、じつはこういう内容だったのだ。 ともあれ北里が録音して残してくれた音声資料は、台湾原住民にしろ、フィリピンの言語にしろ、すべて今でもまだ使われている言語ばかりである。シラヤ語やカバラン語のように、当時すでに死語になりかけていた原住民(つまり平埔族)諸語もあったから、それらの言語を録音しておいてくれたらどんなに有難かったことだろうかと思うのだが、北里の目的がそういうことではなかった以上、それは望む方が間違っている。 北里蝋管でもアイヌ語の方では、偶然にもピウスツの流刑時代の盲目の妻チュフサンマの歌声が録音されていたという劇的な発見があったが、南の方は自由に現地に行って確かめることができない事情もあり、まだ大発見には至らないのである。 最近では録音機器も普通のテープからDAT(Digital Audio Taperecorder)に、さらにはMD(Mini Disk)へと進化し、こちらの方が追いつかない。しかし録音するのは簡単でも、それを文字化するには多大の時間と忍耐と、そしてインフォーマントの協力が欠かせない。それがなかなかできないから、私にもテープの山が残るばかりである。30数年を経たテープは、すでに復元不能なほどノイズが入って、利用を困難にしている。北里蝋管の内容に、文句を言っている場合ではないのである。 本稿は「蝋管こぼれ話」『月刊言語』19.6:54-57 (大修館、1990.05)に多少の加筆訂正を加えたものである。 第3章の記載内容の多くは、主に國學院大學の校史に掲載されている國學院大學教授の益井邦夫先生がまとめられた「日本語源学の泰斗②」國學院大學発行・校史Vol.13 平成13年8月発行を転用させていただきました。ここに改めて感謝の意を表します。 |
|||
|
|
|||