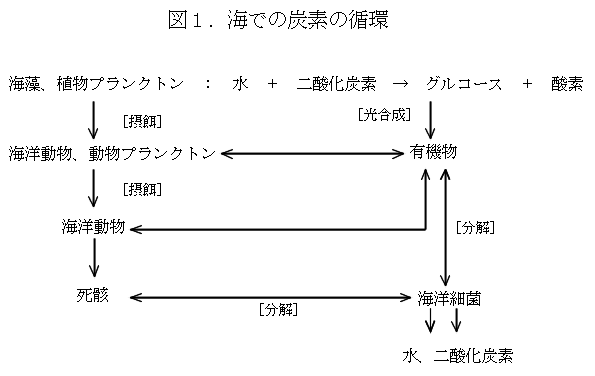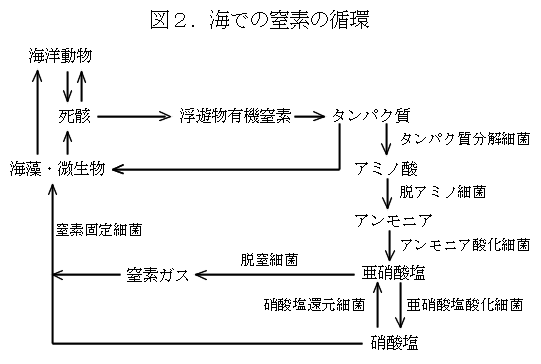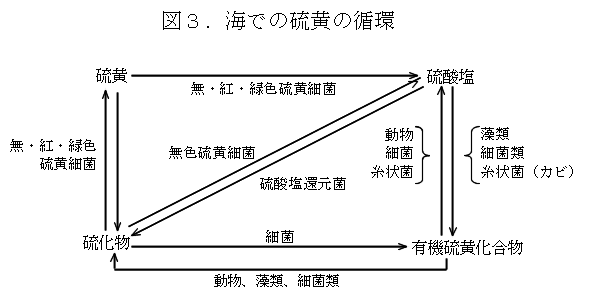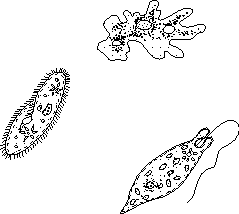|
�@
�@�����̐��������͂��̌��ۂɂ���āA�Q�ɕ������Ă��܂��B��͍����̃z�^���⌴�������̖�����Ȃǂ̂悤�ɁA�̓��Ŕ�������������ꍇ���זE�������Ƃ����܂��B����A�b�k�ނ̃E�~�{�^���Ȃǂ̂悤�ɁA������������������̊O�֏o�Ă������ꍇ���זE�O�����Ƃ����܂��B
�@
�@���������̂����Ȕ����̓��V�t�F�����Ƃ��������ɁA���V�t�G���[�[�Ƃ����y�f�������A�����Ő����鉻�w�G�l���M�[�ɂ���Ă����锭���ł��B����͔M���o�Ȃ��̂Łu����v�Ƃ����Ă��܂��B���������͓��{�ł͂����ɖ��É���w�̕��c�`�������̖剺�Ō�������A�E�~�z�^���̃��V�t�F�����̌������A�\���A�����̎d�g�݂Ȃǂ����炩�ɂ���܂����B
�@
�@�Ƃ���ŁA�C�̔��������̒��ŁA���ƃC�J�͓����悤�Ȕ����̎d�g�݂������Ă���̂ł��B���̎d�g�݂́A�n�_�J�C���V��z�^���C�J�̂悤�ɁA�@�̓��ɓƎ��̔����튯�������́A�E�~�{�^����M���I�r�C�J�Ȃǂ̂悤�ɁA�A�h������Ƒ̊O�֔����t���o�����́A�`���E�`���A���R�E�̂悤�ɇB����������������t���o�����́A�}�c�J�T�E�I��~�~�C�J�ȂǑ����̃C�J�Ɍ�����悤���C�����ۂ����������Ĕ���������́A�c�}�O���C�V���`��L�������h�L�̂悤�ɁA�E�~�{�^���┭���G�r�Ȃǂ̍b�k�ނ�H�ׂāA���̇D�b�k�ނ̔������������Ƃɂ��Ĕ���������́A�̂T�^�ɕ������܂��B
�@
�@���̂悤�ɁA�C�̔��������ɂ���������������̌`�Ŋւ���Ă���̂ł����A��������������̑����̓v�����N�g���Ƃ��ĒP�ƂŐ������Ă��܂��B���ɂ́A���������̃q�J���{���A�o�������̃N�V�N���Q��b�k�ނ̃I�L�A�~�A�R�y�|�[�_�A�E�~�{�^���A�`�����̃I���M�S�J�C�ȂǁA����`�̓����v�����N�g�����������܂����A���̂قƂ�ǂ�����������ۂȂǂ̔����ȃv�����N�g���ł��B
�@
�@���������̖�����͊C�ɐ�������P�זE�̉Q�ږё���1��ŁA�������g�F�����Ă��Ĉُ�ɔ�������ƐԒ����������܂����A����͋��Ƃɔ�Q�͂���܂���B ��������C�̌��������ɂ͂ق��ɕ��U���i�ق����イ�j���m���Ă��܂��B
�@
�@����A��������C�m�ۂɂ��ẮA��ނ������ꎞ�͕��ނ��������܂������A���݂̓r�u���I�A�t�H�g�o�N�e���E���A���V�o�N�e���E���̂R���A�T��ɓ��ꂳ��Ă��܂��B�����ۂ͔|�{����͌����ɐ����������܂����A�������Ɣ������Ȃ��Ȃ�܂��B���̔���������ɂ͎_�f���K�v�ŁA��C�����A���v���ɕۑ����Ă����A�S�N��ɃA���v�����J�����Ď_�f�����������Ƃ���A���������A����ɋ��������ƂɁA�Ȃ�ƂQ�W�N�Ԃ������Ă����Ƃ���������܂��B
�@
�@�����ۂ͐�ɏq�ׂ��悤�ɁA�C�J�⋛�ނ̔����튯�ɋ���������A�L�@���ɕt��������A�Ƃ��ɂ͎�����ނɊ���ꍇ������܂��B�����Ă�������C�J����ɐ�������̂́A���̊��������ۂ����B���邩��ł��B�������A����̔����ۂ�����̋���ނɊ���d�g�݂͂܂�����܂���B
�@
�@���̂悤�ɁA���������͑�ϋ����������錻�ۂł��B�����A���̐��������̎d�g�݂���`�q�̃��x���ʼn𖾂����A�o�C�I�e�N�m���W�[�̈ꕪ��Ƃ��ĔM��Ȃ��������p�������̂����ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@
�@���̖��͕M�҂��{�����������P�N�W������Ɏ������܂����B�I�����N���Q������o���ꂽ�ΐF�u���^���p�N���iGFP)�����������č��̃E�b�Y�z�[���C�m�����w��������Ȍ������̉������i�����ށj���m��2008�N�̃m�[�x�����w�܂���܂��ꂽ�Ƃ����r�b�N�j���[�X�͂܂��L���ɐV�������ł��B
�@�������m�͑O�ɏq�ׂ����É���w�̕��c�������ŁA�E�~�z�^���̃��V�t�F�����̌������ɐ������A�n�Č�A��40�N�O��1960�N��ɃI�����N���Q�̌u�����������������̂ł��B���̌�A���̕������ق��̃^���o�N���ƌ������Ču�����o�����Ƃ���A���i����j�̓]�ڂׂ���A��`�q�̑g�ݑւ������ɂ��p������悤�ɂȂ�A�����̓A���c�n�C�}�[�a�ⓜ�A�a�̌����ɂ����p����铹���J�������ƂŁA���{�l�Ƃ��ĂT�l�ڂ̉��w�܂ɋP���܂����B
�@
�W�D��̐[�C����
�@�����������^���ÂȐ[�C�ɂ́A�[�C�����͂��ߗl�X�Ȑ������������Ă��܂��B�ߔN�A���������ɂ��ς���[�C��������L�l�E���l�T���i���j�@�����B���āA�[�C�̓䂪���炩�ɂȂ����܂��B
�@
�@�P�X�U�O�N�ɃA�����J�́u�o�`�X�J�[�t�E�g���G�X�e�Q���v�����E�ōł��[�������m�̃}���A�i�C�a(��������)�ɂ���g���G�X�e�C���i��������j�i�P�O,�X�P�U���[�g��) ����A���̐[�C�ɂ����������邱�Ƃ�����܂����B
�@
�@���̌�A�A�����J�́u�A�����B�����v���������m�̃��L�V�R�����[���Q,�U�O�O���[�g���̐[�C����A�����̊C��i�����ꂢ�j(�C��̎R��)�̔M�����o�E(���S�������x�͂R�T�O��)�� �߂��ŁA�M���Ƒ͐ϕ����̎悵�Ē��ׂāA�D�M�ۂ̂P������^����(���^���������)����������܂����B���^�������ۂɂ��ẮA�u�V���[�Y�@���̂S�@��͂Q�v�ŏq�ׂ܂��B
�@
 �@�����\���N�̊ԂɁA���{�ł��A�����J�Ƃ̋��������ŁA�[�C�̕s�v�c�Ȑ������������Ŕ�������Ă��܂��B�P�X�X�W�N�ɊC�m�Ȋw�Z�p�Z���^�[�̐��������D�u�����U�O�O�O�v ���P,�X�S�O�`�S,�V�R�O���[�g���̐[�C�ŁA�S�����V���[�g�������鋐��C�J�̎B�e�ɐ������Ă��܂��B�ŋ߁A���ɋ���C�J���ߊl���ꂽ�ƃe���r�ł����܂����B �@�����\���N�̊ԂɁA���{�ł��A�����J�Ƃ̋��������ŁA�[�C�̕s�v�c�Ȑ������������Ŕ�������Ă��܂��B�P�X�X�W�N�ɊC�m�Ȋw�Z�p�Z���^�[�̐��������D�u�����U�O�O�O�v ���P,�X�S�O�`�S,�V�R�O���[�g���̐[�C�ŁA�S�����V���[�g�������鋐��C�J�̎B�e�ɐ������Ă��܂��B�ŋ߁A���ɋ���C�J���ߊl���ꂽ�ƃe���r�ł����܂����B
�@
�@�܂��A�Q�O�O�O�N�ɂ͓��{�̓��Z���^�[�̖��l�T���@�u���������v�ɂ���āA�C���h�m�̃}�_�K�X�J������������Q,�T�O�O���[�g���̐[�C��̂R�O�O���ȏ�̔M�����o�E�ŁA�S�g�������A�Ⴊ�قƂ�Ǒމ������V��̃G�r�i�S�`�U�Z���`���[�g���j����������܂����B���̂ق��ɂ��A�J�j�A�C�\�M���`���N�⊪�L�Ȃǂ̐[�C�������������Ă��܂��B
�@
�@�Q�O�O�U�N �A�쓌�����m�̃C�[�X�^�[���i�o�X�N�A���j�암�̐[�C�̔M�����o�E�t�߂���́A�͂��݂�r�����тɔ��ꂽ�V��̃G�r���A�܂��A�n���C�����̃J�l�~���n�C�ʂ̐[�C����́A�Ԃ�ɍʂ�ꂽ�������V��̃G�r����������܂����B�����̍b�k�ނ̓v�����N�g����ۂ��a�ɂ��Ă���ƍl�����Ă��܂��B
�@
�@�ŋ߁A���[�Q,�O�O�O���[�g���̐[�C�̔M�����o�E�t�߂ŁA�Q�����Ă���n�I�����V(�`���[�u���[��)��V���E���K�C��������܂����B����ɁA�����̑̓��ɂ́A����(�C�I�E)�_���ۂ����������Ă��邱�Ƃ�����܂����B���̍ۂ��������f�Ȃǂ̗������������_�����āA���̃G�l���M�[�ŗL�@��������A���̗L�@�����h�{���ɂ��āA�[�C�̓���Ȋ��Ő����Ă���ƍl�����Ă��܂��B
�@
 �@�[�C�Ƃ����A�j�z���E�i�M�͂ǂ��Ő��܂��̂�? �Ƃ������Ƃ͒����Ԃ̓�ł����B���̓��ǂ��ĂQ�O�N�A���ɂQ�O�O�T�N�ɂ��̎Y���ꏊ������C�m�������̒˖{����������ɂ���ē˂��~�߂��܂����B���̏ꏊ�͐������m�̃O�A�����̖k����Q�O�O�L�����[�g���̃X���K�C�R�̂�����Ɠ��肳��܂����B�X���K�C�R(�R���͊C�ʉ���S�O���[�g��)�̓}���A�i�C�a�ɋ߂��A���̊C�R�̎��ӂ͐��[��R,�O�O�O���[�g���̍L���C��ł��B�ߊl���ꂽ�̂̓v���E���v�g�Z�t�A���X�Ƃ����a����������̗c���i�S���͂S.�Q�`�U.�T�~�����[�g���j�ł��B �@�[�C�Ƃ����A�j�z���E�i�M�͂ǂ��Ő��܂��̂�? �Ƃ������Ƃ͒����Ԃ̓�ł����B���̓��ǂ��ĂQ�O�N�A���ɂQ�O�O�T�N�ɂ��̎Y���ꏊ������C�m�������̒˖{����������ɂ���ē˂��~�߂��܂����B���̏ꏊ�͐������m�̃O�A�����̖k����Q�O�O�L�����[�g���̃X���K�C�R�̂�����Ɠ��肳��܂����B�X���K�C�R(�R���͊C�ʉ���S�O���[�g��)�̓}���A�i�C�a�ɋ߂��A���̊C�R�̎��ӂ͐��[��R,�O�O�O���[�g���̍L���C��ł��B�ߊl���ꂽ�̂̓v���E���v�g�Z�t�A���X�Ƃ����a����������̗c���i�S���͂S.�Q�`�U.�T�~�����[�g���j�ł��B
�@
�@���{�⒆���ŗ{�B����Ă���E�i�M�̒t��(�V���X�E�i�M) �͉��݂ō̎悳��܂����A���̒t�����͂邩�O�A�������̐[�C�Ő��܂�A�t�B���s���������p�E ���������o�āA���{�̉��݂ɂ��ǂ蒅���A�����ɂȂ��Đ�ւ̂ڂ��Ă���Ƃ��� �E�i�M�̉�V�o�H(�����䂤������)�͎��ɑs��ł��B���̒t���������ȊC�m�v�����N�g����ߐH���Đ�������ƍl�����Ă��܂��B
�@
�@���̂悤�ɁA�������͐[�C�����Ƃ��[���ւ�肪����̂ł����A���̐��Ԃ̌����͎n�܂�������ŁA�܂��܂���ɕ�܂ꂽ���E�ł��B
�@
�X�D�H���A���Ɣ�����
�@����܂ŏq�ׂ��悤�ɁA�C�͂܂��ɐ����̕�ɂł��B�����āA�����̐��������[�ɂȂ�ƁA�ĂъC�m�ۂ��������āA���̗L�@�����h�{���Ƃ��Đ��炷��̂ł��B�������āA�C�ł͔����������荂���ȓ��A���܂ŁA�݂��Ɋ֘A�������Đ����Ă��܂��B������C�́u�H���A���v�Ƃ����܂��B�C�̔��������̑��������� �������𗘗p���Ă���̂��A�u�H���A���v�̓���ȗ�Ƃ�����ł��傤�B
�@
�@���̂悤�ɁA�C�m�������͊C�̐��Ԍn�̒�ӂŁA�������Ɠ��������Y���ƂȂ��āA���̑����̐����̖����x���������S���Ă���̂ł��B���́u�H���A���v�ɂ́u�����̏z���v�Ƃ������ʂ�����܂��̂ŁA���͂���ɂ��ďq�ׂ܂��傤�B
�@
��O�́@�����̏z�Ɣ������̓���
�P�D�Y�f�̏z��
�@�O�̍��ł͊C�̐��Ԍn����݂��������̖�����b���܂������A�����ł́A�����̏z�Ƃ�����������������̓������l���܂��B
�@�n����̐����͂��ׂėL�@�I�ȒY�f����������ł��Ă��܂��B���̂������Ƃ͑�C�␅�̒��ɑ��݂����_���Y�f�ł��B���̊C���ɗn���Ă�����_���Y�f���C����A���v�����N�g�����������̍�p�ŁA�Ԃǂ����i�O���R�[�X)�Ǝ_�f�ɕς��܂��B�����āA�A���̓��ł͂Ԃǂ��������X�̗L�@�����ł��܂��B
�@
�@����A�����͂��̗L�@����Y�f���ɂ��āA�ċz��p�Ŏ�X�̑̓��������������܂����A�ꕔ�̒Y�f�͓�_���Y�f�̌`��L�@���̂܂ܑ̊O�֏o�܂��B�����ŁA�����̗L�@��������̂Ȃǂ��C�m�ۂ��������đ̓��֎�荞�݂܂��B�����āA�L�@�Y�f�͍ŏI�I�ɂ͖��@���̓�_���Y�f�ɖ߂�̂ł��B������u�Y�f�̏z���v�Ƃ����܂��B�@
�@
�Q�D���f�̏z��
�@��C�̂T���̂S���߂钂�f�́A�C����C��̑͐�(��������)���ɂ��n���Ă��܂��B�������f�͊C�̒��f���Œ肷���ۂ◕���ɂ���Ď�荞�܂�A���̑̓����A�����j�A����A�~�m�_�ɕω����āA���G���^���p�N����j�_�ɂȂ�܂��B
�@
�@�����̔������͓����v�����N�g���ɕߐH����āA���̉h�{���ɂȂ�܂����A�A�f��A�����j�A�̌`�ő̊O�֏o�܂��B�܂��A�����̎��[���̃^���p�N���͍�(�^���p�N�������ۂƒE�A�~�m��)�ɂ���āA����������A�����j�A�ɂȂ�܂��B
�@
�@
�@��ʂɁA�A�����j�A�͐����ɂƂ��Ă͗L�Q�ł��B�Ƃ��낪�A���̃A�����j�A���_�f�Ŏ_�����āA���Ɏ_���ɂ��āA������Ɏ_���܂ŕω��������ɉ���(�A�����j�A�_���ۂƈ��Ɏ_���_����)�����܂�����A�C�̐����ɂƂ��Ă͍D�s���ł��B�������� �A�L�@���f����ĂяɎ_���̌`�Ŗ��@���f�֖߂�܂��B�����ŁA���̏Ɏ_���𒂑f���ɂ���C���A�A���v�����N�g����ۂȂǂ��z�����܂��B
�@
�@�܂��A�Ɏ_���͍�(�Ɏ_���Ҍ���)�ɂ�������Ɏ_�ɖ߂�܂��B�����ŁA���Ɏ_���͊C��̑͐ϕ��ɂ����(�E����)�ɂ���āA���f�K�X�Ƃ��ĕ��o����A���̃T�C�N�����J��Ԃ���Ă��܂��B������u���f�̏z���v�Ƃ����܂��B
�@
�R�D����(�C�I�E)�̏z��
�@����Ɠ����悤�ɁA�C���ł��Y�f�⒂�f�̂ق��ɗ�������̏z������A�����̏z�ɍۂ��d�v�ȓ��������Ă���̂ł��B
�@�C��̑͐ϕ��ɂ͑��ʂ̐������[���������Ă��܂��B���̗L�@���͊C�m�����ɂ���ď������ꂽ��A��ʂ̊C�m�ۂɂ���ĕ�������܂��B���̎��A�������܂L�@���������������f�ɕω����܂��B�����ŁA������_���E��������ʂ̍ۂ������܂��B
�@
�@
�@�����������������_�����Ă��̃G�l���M�[�Ő��炷��ۂ��������Ƃ����܂��B�����ۂɂ͎_�f�������(�D�C�I)�ŗ������������_�����閳�F�̗����ہi�`�I�o�`���X�Ȃǁj�ƁA�_�f���Ȃ���(���C�I)�ŗ������������_�����āA�������Ő��炷��g�F�i�N���}�`�E���j��ΐF�i�N�����r�E���j�̗����ۂɕ������܂��B
�@
�@�C�ł͂����������ۂ����������_�����ė����ɂ��܂����A����ɗ����ۂɂ���Ď_�����i�ނƁA���_���ɂȂ��ĊC�����ɗn�����݂܂��B���F�̗����ۂ̒��ɂ́A�������������זE���ɗ����Ƃ��Ē~�ς���^�C�v������܂��B
�@
�@�܂��A�ꕔ�̗������͗����ۂɂ�������ڗ��_���֎_������܂��B�܂��A���̗��_�������_���Ҍ����Ƃ���ۂɂ�����������֊Ҍ�����܂��B
�@
�@�����ŁA�C�����ɗn�������_���ށA�A���v�����N�g���A��ʂ̊C�m�ۂ�J�r�Ȃǂ����@�h�{���́[�Ƃ��đ̓��֎�荞��ő��B���܂��B�����āA�����̐����ɂ���L�@�������������A�Ăт��̃T�C�N���֓���̂ł��B������u�����̏z���v�Ƃ����܂��B
�@�M�҂��Q�O�N�O�ɁA���̗����ۂׂ��o��������܂��B����͓�O�����݂̘p���̂��鋛�ޗ{�B������(������)�̊C�ꂪ�A��ʂɔ������Ŕ��ꂽ���Ƃ�����܂����B �������f�̏L�������邻�̍����C��̓D����P��̍ۂ����āA���ꂪ�x�b�M�A�g�A�Ƃ����D�C�I�ȗ����ۂł��邱�Ƃ�����܂����B
�@
�@�܂�A���̂悤�ȗ{�B�����łł́A�a�̎c�肩���⋛�̎��[�Ȃǂ��C��ɒ��ς��܂��B�����ɓK�x�Ȏ_�f������ƁA�����̗L�@������ʊC�m�ۂ��������āA�������f���������č������������ł��܂��B�����ŁA���̗��������_�����闰���ۂ̃x�b�M�A�g�A�����B���āA��ʂɔ��������ł����̂ł��B�x�b�M�A�g�A�͎���̍ۂŁA�̓��ɗ�����~�ς��܂��̂ŁA���̑�W���������������̂ł��B���̂悤�Ȍ��ۂ͊C�����������p�̊C�ꂪ�x�h�{�����Ă����܂��B
�@
�@�x�b�M�A�g�A���C�́u�����̏z�v�Ɉ���Ă���ۂł����A����ɂ����̊����{�B�����^�ł���ƕʖ��ł��B���̏�Ԃ������ƁA�{�B���ނɈ��e�����y�ڂ��܂�����A�C��y�����炦�Ď�菜������(�����)��K�x�̋��a(���イ��)�Ȃǂ̑K�v�ł��B���̂悤�ɁA����Ɍ�����C�ł��A�C�������ς��ƕʂ̓���Ȕ������������܂��B���̌��ۂ��L���Ӗ��Ŏ��R�E�ł́u�ی����(�����������傤)�v�̈�Ƃ�����ł��傤�B���ɁA�C�����ُ�ɕω����錻�ۂɂ��ďq�ׂ܂��B
�@
��l�́@�C�����ُ̈팻��
�P�D�Ԓ��i���������j
�@���݂̊C�����ˑR�Ԃ��ω����錻�ۂ́A�O���ł͌Â������ɋL�^����A���{�ł͓ޗǎ���̏�������m���Ă����Ƃ����Ă��܂��B�Ԓ�����������ƁA��������ނ���ʂɎ���ŁA���Ƃɑ傫�Ȕ�Q�������炵�܂��̂ŁA�C�����̈����̓T�^�I�ȗ�Ƃ��āA���E�I�ɂ��傫�Ȗ��ƂȂ��Ă��܂��B
�@
�@�Ԓ��Ƃ͂����ɔ����ȐA���v�����N�g���̑呝�B�ɂ���āA�C�ʂ��Ԃ��Ȃ錻���������܂��B�������A���̐F�͐ԐF�����łȂ��A�����ɂȂ�A���v�����N�g���̍זE���Ɋ܂܂��F�f�ɂ���āA���F�A���F�A�ΐF�A�s���N�F�ɂ��Ȃ�܂��B
�@�Ԓ��̌����ɂȂ�A���v�����N�g���͂����ɒP�זE�̌]��(��������)�ށA�Q�ږё�(�����ׂ��������)�ށA���t�B�h���ށA�n�v�g���ނȂǂ��m���Ă��܂��B�O�ɏq�ׂ������v�����N�g���̂P��ŁA�Q�ږё��ނ̖����(�₱�����イ)�͔�Q�̂Ȃ��Ԓ��̌����ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�@
�@�Ԓ��͍L���S���E�ɂ���сA�����m�A�C���h�m�A�吼�m�A�n���C�̉��݂���p�ɑ����������Ă��܂��B���{�ł͂����ɑ����m�A���˓��C�A�L���C�̉��݂Ƙp������{�C���̐V���ȓ�̉��݂┎���p�ł��������Ă��܂��B
�@
�@�A���v�����N�g���͌��A���x�A�h�{���A�C���̒�Ȃǂ̏��������낤�ƁA�����I�ɑ呝�B���āA�Ő����ɂ͊C���P�~�����b�g��������A���炩�琔���̍זE�ɒB���܂��B�Ƃ��ɁA�����p����H��p�������ꂱ�ޕx�h�{���������p�ł́A�t����Ăɂ����ĐԒ����������₷���Ƃ����Ă��܂��B
�@
�@����ނ���ʂɎ��ʌ����͗n���_�f�̌��R�Ȃǂɂ�钂������A�v�����N�g����ۂ��o���L�ŕ����ɂ��ƍl�����Ă��܂����A�Ԓ������̃��J�j�Y���͑����̗v�������G�ɊW���Ă��܂��̂ŁA�܂��\���ɉ𖾂���Ă��܂���B
�@
�\�U�D�A���v�����N�g���ɂ��C�ُ̈팻��
|

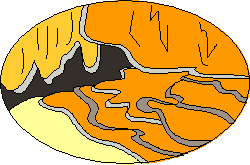 �n�ɂȂ��āA�ΊD���嗝���ɂȂ����ƍl�����Ă��܂��B�����āA�����N����o�ď��X�ɐ��̐N�H(���傭)��p�ŋ�(�����ǂ�)�ɂȂ����̂��e�n�ɂ���ߓ���(���傤�ɂ䂤�ǂ�)�ł��B��茧�̈��Ɠ�(�������ǂ�) �͂Q�O�O�U�N�̍Ē����łQ�R.�V�L�����[�g��������A���{�ōł��������A(�ǂ�����)�ł��邱�Ƃ�����܂����B
�n�ɂȂ��āA�ΊD���嗝���ɂȂ����ƍl�����Ă��܂��B�����āA�����N����o�ď��X�ɐ��̐N�H(���傭)��p�ŋ�(�����ǂ�)�ɂȂ����̂��e�n�ɂ���ߓ���(���傤�ɂ䂤�ǂ�)�ł��B��茧�̈��Ɠ�(�������ǂ�) �͂Q�O�O�U�N�̍Ē����łQ�R.�V�L�����[�g��������A���{�ōł��������A(�ǂ�����)�ł��邱�Ƃ�����܂����B
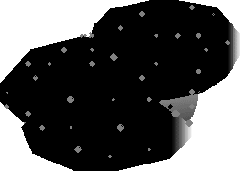 �Ă��܂��B�����m�̐[�C��ɂ́A�}���K���c��(����)�Ƃ���A�����Ƀ}���K���̎_��������Ȃ闱�����邱�Ƃ��m���Ă��܂��B���̃}���K���c�ł��������͐[�C�̋������z���������ȍۂ̍�p�ł���Ƃ��������L�͂ł��B�܂��A�P�X�X�R�N�ɋ��ʎY�Ȃ̎l���H�ƋZ�p�������ŊC������A�d�r��N�[���[�̔M�����ނȂǂɎg���Ă��郊�`�E�����ʂɍ̎悷�邱�Ƃɐ������܂����B
�Ă��܂��B�����m�̐[�C��ɂ́A�}���K���c��(����)�Ƃ���A�����Ƀ}���K���̎_��������Ȃ闱�����邱�Ƃ��m���Ă��܂��B���̃}���K���c�ł��������͐[�C�̋������z���������ȍۂ̍�p�ł���Ƃ��������L�͂ł��B�܂��A�P�X�X�R�N�ɋ��ʎY�Ȃ̎l���H�ƋZ�p�������ŊC������A�d�r��N�[���[�̔M�����ނȂǂɎg���Ă��郊�`�E�����ʂɍ̎悷�邱�Ƃɐ������܂����B
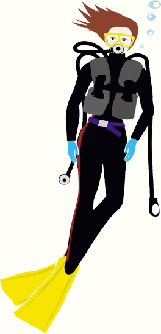 �ɍ���������������܂��B���E���̊C�̕��ς̐[���͂R,�W�O�O���[�g���ł��B�[���R,�O�O�O�`�S,�O�O�O���[�g���̐[�C�͊C�S�̂̂R�R������Ƃ����Ă��܂��B�ł��[���C��͑����m�̃}���A�i�C�a�i���������j�ŁA���ł��P�X�T�V�N�Ƀ\�A�D�u���B�`���[�W���v�ɂ���Ĕ������ꂽ���B�`���[�W�C��(��������)�͂P�P,�O�R�S���[�g���ŁA�����̐������P,�O�O�O�C���ȏ��ɂȂ�܂��B
�ɍ���������������܂��B���E���̊C�̕��ς̐[���͂R,�W�O�O���[�g���ł��B�[���R,�O�O�O�`�S,�O�O�O���[�g���̐[�C�͊C�S�̂̂R�R������Ƃ����Ă��܂��B�ł��[���C��͑����m�̃}���A�i�C�a�i���������j�ŁA���ł��P�X�T�V�N�Ƀ\�A�D�u���B�`���[�W���v�ɂ���Ĕ������ꂽ���B�`���[�W�C��(��������)�͂P�P,�O�R�S���[�g���ŁA�����̐������P,�O�O�O�C���ȏ��ɂȂ�܂��B
 �@�����\���N�̊ԂɁA���{�ł��A�����J�Ƃ̋��������ŁA�[�C�̕s�v�c�Ȑ������������Ŕ�������Ă��܂��B�P�X�X�W�N�ɊC�m�Ȋw�Z�p�Z���^�[�̐��������D�u�����U�O�O�O�v ���P,�X�S�O�`�S,�V�R�O���[�g���̐[�C�ŁA�S�����V���[�g�������鋐��C�J�̎B�e�ɐ������Ă��܂��B�ŋ߁A���ɋ���C�J���ߊl���ꂽ�ƃe���r�ł����܂����B
�@�����\���N�̊ԂɁA���{�ł��A�����J�Ƃ̋��������ŁA�[�C�̕s�v�c�Ȑ������������Ŕ�������Ă��܂��B�P�X�X�W�N�ɊC�m�Ȋw�Z�p�Z���^�[�̐��������D�u�����U�O�O�O�v ���P,�X�S�O�`�S,�V�R�O���[�g���̐[�C�ŁA�S�����V���[�g�������鋐��C�J�̎B�e�ɐ������Ă��܂��B�ŋ߁A���ɋ���C�J���ߊl���ꂽ�ƃe���r�ł����܂����B
 �@�[�C�Ƃ����A�j�z���E�i�M�͂ǂ��Ő��܂��̂�? �Ƃ������Ƃ͒����Ԃ̓�ł����B���̓��ǂ��ĂQ�O�N�A���ɂQ�O�O�T�N�ɂ��̎Y���ꏊ������C�m�������̒˖{����������ɂ���ē˂��~�߂��܂����B���̏ꏊ�͐������m�̃O�A�����̖k����Q�O�O�L�����[�g���̃X���K�C�R�̂�����Ɠ��肳��܂����B�X���K�C�R(�R���͊C�ʉ���S�O���[�g��)�̓}���A�i�C�a�ɋ߂��A���̊C�R�̎��ӂ͐��[��R,�O�O�O���[�g���̍L���C��ł��B�ߊl���ꂽ�̂̓v���E���v�g�Z�t�A���X�Ƃ����a����������̗c���i�S���͂S.�Q�`�U.�T�~�����[�g���j�ł��B
�@�[�C�Ƃ����A�j�z���E�i�M�͂ǂ��Ő��܂��̂�? �Ƃ������Ƃ͒����Ԃ̓�ł����B���̓��ǂ��ĂQ�O�N�A���ɂQ�O�O�T�N�ɂ��̎Y���ꏊ������C�m�������̒˖{����������ɂ���ē˂��~�߂��܂����B���̏ꏊ�͐������m�̃O�A�����̖k����Q�O�O�L�����[�g���̃X���K�C�R�̂�����Ɠ��肳��܂����B�X���K�C�R(�R���͊C�ʉ���S�O���[�g��)�̓}���A�i�C�a�ɋ߂��A���̊C�R�̎��ӂ͐��[��R,�O�O�O���[�g���̍L���C��ł��B�ߊl���ꂽ�̂̓v���E���v�g�Z�t�A���X�Ƃ����a����������̗c���i�S���͂S.�Q�`�U.�T�~�����[�g���j�ł��B